|
mitsuruゼミナール
| 入塾のススメ |
|
あの頃の思い出
このホームページの人口1000番記念に、キリ番ゲッターから施設とエッセイのテーマを訊いたところ、「塾」という要請がきた。
元々この村には学生街はあれど開店休業状態だった。理由は学生生活を書くことがとても精神的プレッシャーとなっていたから。別に嫌なことがあった訳ではなく、生活は総じて幸福なものだったが、それだけに書くのがつらいのだ。
そこへ塾の依頼がきた。
そもそも塾なんて全然考えてはいなかったのだが、よくよく考えて みれば小学校5年生の9月から小学校6年生の1月まで通った進学塾での生活は僕の人生を変えるほどの影響があったのだ。
この思い出を僕はこれから書こうと思う。
云っておくが、僕はこの1年半の時期ほど勉強したことは先にも後にもない。よく僕を「物知り」だの「雑学狂」だの褒めて(?)くれる人はいるが、何のことはない、この頃の受け売りである。
高校・大学と入試はほとんど勉強しなかった。英語は惨憺たる成績だったがあの頃学んだ国社で全部カバーした。
それくらい僕は勉強漬けの日々だった。はっきり云うと中学入試に向けた進学塾は遊び呆けた高校生よりも余程高度な学問をやる。夏休み、最高で1日に10時間もの勉強をやった。
そんな生活だったが、意外なほど楽しかったし、色々と喜怒哀楽の事件もあった。記憶が不鮮明の為、時期などについては誤りがあるかもしれないが事件そのものは真実である。
進学塾に行く人、また未知の人、これからの人。
みんなに楽しんでもらえると思う。 ▲
|
| 赤い天狗が青ざめた |
|
劣等生の洗礼
のっけから自慢をかますと、どこにでもある田舎の小学校で、僕は一番頭がよかった。今ではすっかり落ちぶれてしまい、あの頃の同級生にも僕よりいい大学に行った者は「何人か」いるが(ただ今でも総じて馬鹿なのが多いが)、IQ140の僕は向かうところ敵なしの優等生で学校の狭い世界の中で大言壮言していた。
なんといっても周りの平均点より常に20点以上は離して、クラスのトップの座を射止めていたのだ。いや、いい時代だったね。周りが何でこんな簡単な問題が出来ないかいつも不思議で、テストの時などは時間を潰すのに苦労した。
だから僕は「将来、東大を滑り止めで受けるから」とか、成績が2位と3位の奴を捕まえて「俺は東大行くからお前は早稲田、お前は慶応に行け」などと吹聴していた。井の中の蛙とは恐ろしい例えで、クラスの連中も僕の自慢を間に受けていたりする。
救いがたいバカ集団である。
ここにもう一人のバカが登場する。
そんな僕の様子を見て、教育熱心な母親は僕を進学塾に送りこみ息子をエリート街道に乗せようと画策したのだ。我が家は代々地元の名門校の出がほとんどであり、僕をその学校の付属中に入れようという魂胆である。
さすがに私立中受験のためには小学校の勉強だけでは無理という風聞を得、高い学費を先行投資として払い、僕を高貴なる道の一歩を踏ませてくれたのである。
塾は有名進学塾であるからして定員があり、僕は入塾試験なるものを1万円払って受けた。
僕は当然普段学校でやる楽勝テストのノリで行ったのだが、テストを見た瞬間、すっかり血の気が引いてしまった。これがその後の苦闘の前奏曲なのだが、中学入試の過去問らしきその問題は、もうさっぱりまったく見事にわからなかったのだ。
青い顔で答案を返すとしばらく頭を抱えたねえ。
と、数日後、結果が返ってきた。
見ると「入塾許可、Aクラスに配属」とあった。
僕は胸を撫で下ろし「まあ、僕の実力じゃAクラスは当然だよな」と安堵のため息をついた。と、母親の鉄拳が飛んでくる「何、馬鹿げたこといってんの、下を見なさい、下を」と叫んだ。
そこには表があった。
「クラス編成表
C−2(注・後にF)…偏差視60以上
C−1.3…偏差値50以上60未満
A−1.2.3 …偏差値50未満」 ▲
|
| いきなり昇級 |
|
自信回復
入塾の日、僕はおそるおそる教室に入った。
なんといっても学校創立以来の俊英といわれた僕を最下等クラスに配属するなんざおおよそ信じられず、そんな塾なぞ化け者の巣窟に違いないと思っていた。
ところが最下等のAクラスに入ってみると拍子抜けした。
僕はここには1月しかいなかったが、確かにここは酷かった。
いるのは小学生ばかりだから当然なのだが、ほとんど動物園であり以後経験したCクラスの生徒とはとても同年とは思えない物だった。初めは「僕以上に頭がいいんだろうな」と敬意をもって接していたが、どうやら授業を受けてみると彼らは「地元の学校よりは多少マシ」といった程度の薄ら馬鹿らしいと気がついた。
色々聞いてみて、僕がAクラスに配属されたわけがわかった。
僕は9月入塾の途中組で、その入塾試験は月に一度の定例試験の問題を使ったらしい。定期試験というからにはその月にやったことが中心に出るわけであり、まったく専門の勉強をしていない人間が解けるような代物ではない。これが解ければ進学塾など必要ない。
僕はきちんと一月で解法をマスターし、入塾一回目の定例試験では偏差値55をマークし、C−1クラスへの編入を即日許可された。
以後、一度もAクラスには戻らなかった。 ▲
|
| 塾閥C−1クラス |
|
ハッピークラス
いきなり結論から言うとこのC−1(後にC−3、すなわち偏差値 50台)クラスが一番僕の学力にあっており、過ごしやすかった。
実際環境がとてもよく、向学心に燃えてる猛者が何人もいて、各々切磋琢磨の気風が流れていた。
先生も熱心で学力に幅があった為、基礎からやってくれた。その為に中途入学の僕でも実にわかりやすく学校では味わえなかった学習の喜びというのを感じていた。高校に入って後、予備校通学者が高校の悪口を言いまくっていたが、なんとなくわかる。
塾の勉強はとかく色々と批判されるが、僕にしてみれば全くの迷惑である。最近の個別指導と称する集金塾がどうかは知らないのだが、数万円の授業料をとる高度な進学塾ともなると、講師も高給取りの専門職である。時を忘れるほど、学習が楽しいのだ。
もう僕は地元の学校で演じていたような驕りは微塵もなかった。学校では殆ど学問は無視して、図書室から借りたホームズや漫画日本の歴史などを読破していた。
ところで、このC−1クラスは学問楽しさのほかにもうひとつの 財産を築いた。
後の級友である。
地元に大きな私立学校は1つしかなかったせいかこのC(1と3)クラスのメンバーは実際殆どその学校に進んだ。僕は彼らと仲良しで名前くらいは知られていた。
彼らの中の何人とは実に仲良くなり、今でも親交が続いている。
目標中学では入試でも入学式でも知った顔が沢山いる。
まさしく塾閥というものが入学初期には確かに存在した。 ▲
|
| 夜のフシギ |
|
就寝法廃止
我が家は教育熱心な家である。
ただし両親は常識や教養には異常に強いが、必ずしも受験学問には通じていないため、勉強を教えるよりはそのサポートに徹するのが常だった。要は塾をサボって遊んでいると(そんあことは2回しかなかったが)、耳つねって連れ帰るような親である。
とはいっても、勉強を口やかましく言うのは入塾以降で、それまでは生活習慣について厳しくしつけていた。起床就寝の時間、部屋の整理門限、宿題のチェックや落し物、なくし物に交通ルールなどである。
特に厳しいのは就寝時間で平日は8時、週末は9時だった。
だから僕はテレビも見られず、話題についていくのに苦労した。
ところが塾に入ると8時に就寝などと云っていられない。それは母も承知して就寝規則は撤廃された。普通は就寝時間を遅くしそうなものだが、突然撤廃するあたり、なかなか反動的だ。
だから僕はお言葉に甘えて夜は予習復習を欠かさず行った。
1日に塾のない日は3時間、ある日は塾で2時間やるので1時間の追加学習をした。そのお陰で、もう4月入塾の連中と拮抗できる位の学力が年末までについていた。
ある日、僕が勉強を終えて時計を見るとアナログ時計の文字盤が12時を超えるところだった。
僕は生まれて初めて1日の変わる瞬間を体験し、「まだ起きているなんて不思議なものだな」と思って外を見た。保守的な田舎街は既に闇に包まれており、街灯の光だけが輝いていた。 ▲
|
| 3人の社会キチガイ |
|
僕とM
時が過ぎ、僕は塾で若干の有名人になった。
といっても頭がよくて、ではない。
偏差値は文型科目なら60を優に超えていたが、どうしても苦手の算数があがらず、なかなか大台に乗れなかった。僕が有名になった理由は社会が異常に出来たからだ。
これはAクラス時代から先生に認められていたのだけど、小学校の担任の影響かどうか社会科は入塾前から大好きで、よく知っていた。そんな僕のこと定例試験でも、絶好調のときは偏差値が70を超え、マークシートの統一確認テストでも90点を下回ったことがない。
この社会優位だけは塾終了まで変わらなかった。
ある日、先生が「山田とMとSは社会科三人衆だな」と冗談を言い、それが口コミで広まり、最後は神格化めいた話になったのだ。これは嬉しかったね。
この中のMという男は近隣学校でも名の聞こえた変人(?)で、塾でも鉛筆をかじる、指名されたら机を叩いてから挙手するなどの奇行をもった男だった。
僕は初め、近寄りたくないと思ったがこの称号以降よく話をするようになった。と、彼が奇行の反面、噂どおりの頭のよさを持った人間であることを知り、すっかり意気投合して仲良しになった。
よころが、彼は結局受けた中学には全部落ちてしまった。
この報は中学校に入った後、塾生の間でかなり話題になった。
ところが彼はリベンジとして高校に見事入学し、「文芸部員」として僕らと一緒に活動するようになったのだ。
彼はその後の大学受験では苦杯を舐めたが、末期には「日本史では全国模試は最高点が当たり前」「TOEIC750点突破」等の栄誉を得て、苦節の末に一流国公立大学に入った。
今でも、彼は元気だろうか? ▲
|
| 真夜中のタイヤキ |
|
寒い日はアツアツで
当然のことながら、冬は寒い。
塾へは家から数キロ離れていたため、行きは回数券でバスを使い帰りは電話をして家人の車で帰っていた。あの念のため云っておくと電話といっても勿論公衆電話である。当時はポケベルも未だ普及していない。
家人に電話して車がくるまで大体20分近くかかった。
この間それまでの残暑の秋なら耐えられたが、こうも寒くなってくると絶えがたいものがある。
母に相談したところ「寒さが勉学の妨げになるのならば」と一日80円のタイヤキ手当てを支給してくれた。塾の前においしいタイヤキ屋が店を出しており、そこが80円だったのだ。
味はアン・クリーム・チョコ・カレーと均一価格で4種類あり、普段はチョコを、お腹がすいたときはカレーを食べていた。家人を待ちながら湯気の立つアツアツのタイヤキをほお張るのは至福の一時だった。
ゆっくり食べると、包装紙をゴミ箱に投げる頃におめあてのヘッドライトがやってくる。
僕は小走りに駆け寄って、暖房の効いた車にもぐりこむ。
そして「家に帰ったら復習するぞー」と心に固く誓うのだ。
追記;このタイヤキ屋は中高と若干利用したが、先日久しぶりに行ってみたらなくなっていた。代わりに大手のたこ焼き屋が出ていたが、僕は食べる気がしなかった。歳月無常。 ▲
|
| 人体講義に失神した |
|
いやすぎる
情けない話だが、血とか肉とかいう話に非常に弱い。そのせいで昔は一切肉が食えなかったぐらいだ。今では随分堅気になってきたが、食えないものは尚多い。
さらに困るのは女事もあまりよくは…いやいやあんまりこのテの話はよくないので語らない。
まあ、とにかく人体とかも駄目なんだよ!(何故か怒り調)
スプラッターを見ようが、解剖を見ようが、おそらくぶっ倒れる。蛙の解剖程度ならやったが、あれは仲間がそばにいたから見栄張って作業できたわけで、単独だったらゲロを撒き散らしてたろう。事実、うっときたときはあった(ああ、あの胃液の味)。
さて、だから塾だろうが学校だろうがこの話は参ったね。
ちゃんと入試には出るからやらなくっちゃいけないんだけれども微細に渡って解説を入れられるのは最上の苦痛だった。逃げ道はないし耳をふさぐわけにも行かない。
そういう話を聞いているとまず手の力が抜けて鉛筆がもてなくなり、やがて動悸が早くなり、皮膚は急に薄ら寒くなる。
その講義は忘れもしない血液循環の授業で、頚動脈の話になった時のことだ。ある生徒が「首を切られてもしばらくは生きているんですか?」と質問した。そして先生は趣味なのかなんなのか小塚原やギロチンの話を得意げにした。
この回答で僕はすっかり打ちのめされ、挙手し「トイレ行ってきます」と告げた。先生や他のクラスメイトは僕の顔を見て吃驚した。後に僕は自分の顔色が、真っ白だったらしい。
先生の指示で講師控室でしばらく休ませてもらい。暖かいコーヒーをご馳走になった。
これが小学校なら長期間冷やかされるが、塾の生徒は皆レベルが高く、心配の声以外は一切触れられず、勿論からかわれた事は一度もなかった。 ▲
|
| エリートへの道 |
|
僕は切符を手に入れた
まさかね、と僕は驚いて講師控室を出た。
小学校6年生にあがって、すぐの定例試験。僕は先生からC−2クラスへの編入を許された。平均偏差値が2回連続で60をやっと超えられたのだ。
正直云って、嬉しかったが不安のほうが多かった。
なんといってもC−2クラスといえば塾全体の定例試験成績優秀名簿の常連たちが集まっているのだ。それこそ偏差値70オーバーが群れをなしているようなところで、その有名人たるや塾の中で事情通の仲間が「ほら、あの人が**くんだよ」と教えてくれるほどだった。
山田、C−2昇格という報はそれまでのクラスでは驚きをもって 受けいられていた。僕は社会(あと国語)が出来ることでは多少は知られていたが、逆に数学の悲惨さはあまねく知られていたのだ。それに下馬評では僕は可能性はあるが、賭けるのは賢明でない穴馬だったのだ。
事実、今度の昇格人事も、数学が比較的酷くなく、それで平均が押し上げられて60を超えたというところだった。
僕は沢山の仲間から祝福を受けて、C−2クラスに編入した。
今思い返すと確かにC−2クラスは尋常なクラスではなかった。
結果から云えば、このクラスから男子御三家(開成・麻布・武蔵)も女子御三家(女子学園・桜陰・隻葉)も出ていた。あまつさえ開成は2人も出てしまったのだ。
やはりというか、当然というかクラスの雰囲気は大人っぽく、今の僕よりも大人じゃないかと思うことがある。事実、彼らの知的レベルは平均的大学生を凌駕することは間違いない。それでいて人間的魅力も決して失わないのだ。
僕は貧困地区にある学校がいかに狭いものであるかを知った。やはり真のエリートは並みじゃないのだ。
僕の戦争が始まった。 ▲
|
| 賢い女子との再会 |
|
「トゥエルブ」の彼女
C−2の勉強は非常にきつかった。
まあこの話は後に譲ることにして、ここでは僕が新クラスで四苦八苦している時の閑話である。
まず時代は塾など考えもしなかった小学校2年生の時に遡る。当時、病的な反抗児として担任から目を付けられていた僕は仲間とよくプロレスごっこをしていた。プロレスといっても技のかけあいがあるわけではない。殆どただの喧嘩である。
ただ遊びなので本気では殴らないし、せいぜい組み敷いてスリーカウントかける程度の稚拙なものだった。だが燃えた。ガキの偏執性という奴で、僕らは朝早く学校に来るとこの遊技にふけった。
そんなこんなで汗を流したある日、僕らはいつしか英語の話をしていた。多分、カウントのところで出た話だろう。
「ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイトナインテン、
11って何だ?」仲間が訊いた。
「イレブンだろう、セブンイレブンってそういう意味だから」
「ああ、じゃ12はなんだ?」
僕らはすっかり悩んでしまった。誰もそれ以上は知らないのだ。
「トゥエルブ」
声がした。それまでいつも朝早くから来て本を読んでいた転校生の女の子が眼鏡の奥からこっちを見ていた。彼女は驚いたように自分を見る僕らに、歌うように続けた。
「サーティーン、フォーティーン、フィフティーン…」
云っておくが当時の僕はこういう風に聞き取れたわけではない。ただ彼女は正解らしき言葉を呪文のように唱えにっこり微笑んだ。僕らは突然のことに仰天して、返す言葉もなかった。
彼女は父親が転勤族らしく、その年の年末に引っ越していった。
この学校には1年もいなかった。
「山田君……って**小にいたよね?」
だからそう云われたときは本当に吃驚した。僕もその時は転校を経験し、小学校2年生の時とは違う学校に在籍していたからだ。まるで冗談のような話だが、塾で僕は彼女と再会したのである。
「なーに、山田君のこと知ってるの?」
と、彼女の友達が横から興味ありげに口を挟んだ。頭のいい子は往々にしてマセたものである。何人か男子も集まってきたが、勿論「ひゅーひゅーあついねえ」なんて小学校のような馬鹿な真似はしない。
彼女は僕との経緯を話すと、最後にこう付け加えた。
「山田君はねえ、怒ると怖いんだよ。なんといっても先生をほうきで殴って泣かせちゃうんだから」
ま、そういう過去もあったけどね。でも彼女にとって僕の認識はそんなもんか、とちょっとがっかりした。昔、ほのかな恋心の相手としては惨憺たる再会だった。
彼女は偏差値70を常に越え、女子御三家の桜陰に入学した。 ▲
|
| 大学への憧れ |
|
中学模試の大学体験
案外知られていないが中学入試にも模擬試験というのはあって、この会場には近隣の大学が与えられた。塾が一括して申し込みをするので、僕らは電車に乗って目的地に着けばいいだけだ。
僕はこの時が生まれて初めて単身電車に乗ったのである。結果から云えば僕はこの難事業を何とか乗り切った。乗り過ごしも忘れ物もしなかった。小6という年が少々遅れているような気もするが、まあ深い詮索はよそう。
ところで中学模試だからってなめてはいけない。
最寄駅はその大学のために作られたような駅で、大学の門までの一本道のはずっと学生向けの店が並ぶ歓楽街が通っている。その広い道に、驚くなかれ膨大な数の小学生が道一杯いに広がりざわざわと蠢いているのだ。
地図は一応貰っていたが、はっきりいて必要ない。おそらく僕の小学校の全校生徒より遥かに多い人数の小学生が一点目指して歩いているのだ。参考書読んだり、馬鹿話したりしている彼らについて行けば、まず考えずともつくだろう。
実際、やたらとあるコンビニやゲーセンで若干名が吸い込まれていったものの無事大勢に従って、会場の大学に着くことが出来た。
受験票を手に係員の指示に従って教場にはいる。
模試自体は緊張しなかった。僕の志望学校と僕の通常偏差値の間には10の余裕があったからだ。実際、模試の結果も文句なしのA判定だった。
さて僕は模試の終了後、会場で偶然出会った仲間と大学の探検をしたり、学生街でゲーセンに行ったりコンビニで軽いものを摘んだりしていた。
広い教場にキャンパス、施錠されてはいたが沢山のPC、食堂や自販機やいろいろな施設。駅までの学生街にはもうゲーセンからレストランから何でもある。僕はこんな所で毎日を過ごせる大学生というものに強い憧れを感じた。
その憧れは高校3年生まで持っていた。
だが、実際ふたを開けてみると、僕の大学は学生街もろくにないさびれた大学なんですね。この大学とは偏差値が10は違うから、それもやむないとはおもうけど。 ▲
|
| 酷暑極寒 |
|
無いよりゃマシの極寒クーラ
夏とはとても暑いものだ。
ただ普段は塾は夜なので、暑いと云ってもたかがしれたものだが夏期講習が始まると話は別だ。僕はこの頃いつも自習室に篭って
は勉強していた。
自習室を駆使していた理由は二つあって、まず僕のようなC−2にいるとはいえ、頭の出来のよくない人間は死ぬ気でやらないと追いつけない点。そして家にはクーラがないので塾の方が遥かに環境がいいという点があげられる。
今回は後者、曲者のクーラの話である。
塾に限らないが、何故かこういう教育施設はガンガンにクーラをかけるかな。寒い方がやっぱ学習効率がいいからなのだろうか? 先生は「夏期講習がはじまったら暖かい服をもってきなさい」と 逆説的なことを云い、僕らは「何を馬鹿なこといってんだろうな」と内心笑ったが、冗談ではなかった。
外は酷暑で街が揺らめいていても、塾の重い扉を開けると途端に冷気が襲ってくる。爽快だといってられるのはものの5分、体にまとった熱気が吸い取られていずこへと逃げていくのがはっきりと知覚できる。
現場を知らない母などは「こんな厚い服を持ってくの? あんた大丈夫?」と僕の精神的平衡を危ぶむが、野暮用で塾に行って以来、きっぱり口を閉じた。
この冬を思わせる寒さ、それは夏期講習の弁当にも現れており暑さで傷むもなにも口にいれるとひんやり冷たいのだ。
クーラ病の人がいたら死んでしまうような場所ではあるが、僕は一夏の間、自習室(空き教室だったんだけどね)にこもり、寒くてどうしようもないときは長袖のまま外に出て「ううう、やっぱ寒い方がいい」という目に遭い、また戻って震えていた。
こんな目にあっても、家の酷暑の中で勉強するよりは確かに効果はあったと自負している。 ▲
|
| 888作戦 |
|
楽そうに聞こえるけれど?
「夏は受験の天王山」という。
こんなことは私立を受ける子供なら誰でも知っている。しかもある程度以上の頭を持つ子は語源まで知っている。国語の授業では随分慣用句や四字熟語を覚えさせられた。おそらくこの時期と今とでそういう語彙は殆ど増えていないと思う。
言葉に限らず何度も云うように、僕は基本的にこの頃に修得した知識を駆使して、その後の人生を楽して生きてきたのだ。その故か英語は全く出来ないのだが、こうして三流私大には入れている。
はっきりいえば我が大学の日本史なぞあの頃の僕でも合格点をとれるだろう。
さて、そうなるためにはどれくらい勉強すればいいか?
「君たちは、この夏、一日に8時間は遊びなさい」
そう夏休みを前に先生は云った。
生徒は少々ざわめいた。
そして「1日8時間は眠りなさい」とも続けた。
生徒はまたざわついた。睡眠時間は四当五落などという言葉が小学生の癖に流れていたのだ。
最後に「ただし残りの8時間は勉強しなさい」と宣告した。
聞くと簡単そうでしょう?
1日に8時間は遊べて、8時間は眠れるんだから。
ところがこの「888作戦」、いくら夏休みとはいえどもつらすぎる。やってみればすぐ解る。普段は夏期講習の間、5時間は勉強するので、家での3時間は苦ではないが、塾のない日の家で8時間は本当につらい。
やりきったあとは本当に極楽だけどね。
こんなに勉強してもC−2クラスでは僕は落ちこぼれだったのだ。
まったくあいつら何時間やってんだか? ▲
|
| 青春ベジータベータ |
|
アヤシイじゅーす
よく小学生の塾通いを批判する人がよく引き合いに出す例として「深夜にコンビニで、塾帰りらしき小学生が栄養ドリンクを飲んでいる」という比喩があげられる(本当によく引き合いに出される)が今回はこの話である。
と、いっても僕の塾では8時に終わっていたから深夜ではないし、確かに塾は駅前にあり電車通学組もいたが僕は違う。そういう意味では別に僕は以上の言質を咎める気はない。
問題は栄養ドリンクである。
これも厳密に云えば別に我々の間で栄養ドリンクが流行ったという事実はない。ところが、ちょうど僕らが夏期講習に汗を流していた頃、C−2クラスでは奇妙な飲料がブームになっていた。
コカ・コーラ社の「ベジータ・ベータ」である。
自販機にも売られていたそのジュースは珍しく瓶詰めで、200ミリリットルの小瓶に入っていた。色は往年のメロー・イエローを思わせる濃い黄色だった。「ベジータ」という名からわかるとおり、緑黄色野菜のエキスをふんだんに使った滋養分に溢れる「栄養ジュース」というふれこみだった。
この高級感溢れるジュース、これが大受けしたのだ。
あ、値段はその頃は通例と化していた110円だった。
初めはC−2クラスの優等生で、いつも面白いこと云ってクラスをわかせていたY(僕ではない!)が持ち込んで、ジョークの意味を込めてか毎日飲んでいた。みんなは笑いながらもそのジュースに興味関心を持ち、噂の連鎖反応からみんなが飲むようになったのだ。
最盛期には塾の前の自販機からいつも売り切れになるほどの 人気をほこっていた。世間的には「ベジータ」はあまり人気が無いのか、この自販機以外では見かけなかった。その希少性も人気の秘密かもしれない。
僕は夏期講習では母の持たせてくれるブリックを飲んでいたが、ある時好奇心にかられて飲んでみた。
いや、妙な味だったよ。色はオレンジだけど味は異なる。まずいとも違うのだが、とにかく「妙」としかいえない変に甘い人工的な味だった。良薬は口に苦しという慣用句が浮かんだ。
すぐに消えてしまったが、それもわかるようなジュースだった。 ▲
|
| 返らない300円 |
|
社長は信じるな!
僕の通っていた塾はジャンクションである駅前の一等地にあり、その塾の窓から「**建設」という地元では大手のゼネコン企業の本社ビルが見えた。
地方の建設会社のくせに羽振りがいいのか鉄筋ン階建ての自社ビルである。
そういう今が栄華の地方企業の社長子息が、やはりこのC−2クラスに来ていた。まるっきり漫画のパターンだが、背は低いものの目元涼しげな美少年で、頭も秀才クラスの中でさえ、飛び抜けて良かった。そういう奴もいるのである。
さて話は少々変わるが当時は「ストリートファイター2」のブレイクの余波が続いており、今に至る格闘ゲームブームが流行していたときである。当然、小学校6年生の彼らも受験がなんだとばかり夏の暑い中、仲間と誘い合ってゲーセン行脚していた。
僕はそもそもお金がなかったし、あったとしてもジュースアイス費にしていたので、たかだが数十秒で消えるゲームなどに消費する気はなかった。
そんな暑い日、秀才の彼がC−2の友人を連れてやってきた。聞くと「300円かしてくれ」とのこと。どうせ例によってゲーム代に使うんだろうから、僕は躊躇した。いくら普段からつきあっている仲間とはいえ、300円は大金である。
だが、結果的には僕は貸した。友人の「こいつはあのビルの会社を継ぐお坊っちゃんだぜ? 返さないわけがあるかよ」などという甘言に負けたのである。
で、結局どうなったかというと御賢察の通り返ってこなかったのである。僕自身、彼とは色々な意味であまりに差のある人間なので催促しづらかったというのはあるし(脅されたりしたわけではない)彼も雑談はしてもその話はしなかった。
そのまま、なんとなく時は過ぎていって、気がつけば僕はC−2クラスから降等されてしまったのだ。こうなってはもはや逢うこともない。
その後、彼は日本一の難関中学「開成」に行ってしまった。順当に行けば、今頃彼は本郷のキャンパスでふんぞり返っているはずである。
さらにうまく行けば彼は家業を継ぎ、僕は市役所の役人になっているはずだ。公共工事の入札会場であったら、その時彼の払う負債はとても300円じゃ済まないだろう。 ▲
|
| 落ちこぼれ体験記 |
|
どっちがいい?
僕は自分で云うのも変だが、当時、辺境の田舎小学校では抜群の秀才だった。今ではすっかり零落してしまい、「長じて神童の試しなし」の諺の如く、今では同窓生の中でも僕より頭のいい奴は沢山いる。
だが、かつては僕はクラス最高の知識と教養を身につけており、周囲からは羨望と嫉妬の目で見られていたのだ。小学校時代殆ど学校の勉強では苦労をした覚えはない。
その僕が、である。
塾では身分逆転、学校では内心馬鹿にしていた「落ちこぼれ」に堕してしまったのである。名誉のために補足すると日本を代表する中学に進学するC−2クラスでではあるが。
僕の志望校は偏差値50程度、このときの僕の偏差値は60前後で、クラスメイトは概ね65から70、先は天井知らずである。
塾側としては名目は60以上の生徒を収容するクラスといえども60の生徒にあわせていたら、超一流中学に入れるものも入れなくなってしまう。当然、レベルは跳ね上がる。
正直、このC−2クラスはしんどかった。
国語と社会なら何とか対応できた。殊に社会のテストは確かにトップと拮抗していた。だから僕はC−2エリートにも普通の友愛を以て接して貰えたのである。
だが理系科目、特に数学の落ち込みは酷いものがあった。解法の糸口さえわからないのだ。元々いたC−1クラスでさえ出来ないことで有名だったのだ。もう授業も何もさっぱりわからない。解答を見ながらやっても解らない。僕が指名を受けて解くとき、先生は丁寧に解説してくれ、殆ど先生主導の解答を導き出した。重傷なのはそれでも当の僕はさっぱり解らなかったのだ。
C−2クラスにいた数ヶ月、僕は完全な二重生活を送っていた。学校では創立以来の秀才として周りから驚異の目で見られ、塾では再度すべからざる劣等生としてね。
そこで思うのは優等生と劣等生では明らかに優等生の方がいいということだ。何を当たり前なと云われるかもしれないが、これは僕が人生で会得した数少ない真理である。 ▲
|
| 進路決定 |
|
勉強よりも大切なこと
僕の入塾動機は近隣にある私立中学校に入ることだった。まあ厳密に云うと母の指定した「入塾動機」ではあるのだが、それはこの際問わないでおく、結果的には僕の意志とも合致したから。
僕がその学校を希望としたのは小学校とは異なり知的な雰囲気に身を置きたかったことと、当時吹き荒れていた校内暴力と教師側の過酷な生徒指導(例えば男子は丸刈義務だった)から逃れるためである。要は「馬鹿で乱暴なところはやだ!」という甚だ亡命的な理由である。
上昇志向かと思われる母だが、実は母が僕を塾に入れた動機も後に聞くと同じらしい。「規律正しい学校だし、生徒も知的で活気がある」というのが理由だった。
いわゆる伝統名門校であるので、公立中のような殺伐とした感覚とは無縁であり最低限守るべき校則は徹底されていた。各種の教育問題とも無縁であり、インテリ生徒にとっては天国だった。
さて、ところがこういう考え方を持った者は少ない。大抵の父兄は上昇志向の塊で、より高い学校を目指していた。だから志望校を聞くと本人の偏差値とは関係ない大言荘言が聞けたものだ。
そんな中、自分より10も偏差値の低い学校に入りたがる僕は、C−2クラスでは完全に変人扱いだった。志望校を再考するように僕に勧めたのは先生ではなく周りの仲間だったから始末が悪い。
友人たちの再三の説得により僕も何となくその気になってしまい一度母に直談判したことがある。その結果が先に述べた母の進学思想である。母は勉強も勿論だけど、その前に人間として必要な、礼法や人徳、教養を身につけてほしいというのである。
当然、志望校は当初の学校でなければならず、併願も含めて要望は拒否されていた。僕もあまり併願には乗り気ではなかったので、この話はそれで終わり、僕は更に勉強することになった。 ▲
|
| 泣きながらグッバイ |
|
だから違うんだってば!
これは僕の友人でもなかなか理解して貰えない体質なのだが、僕は空気の悪いところに来ると涙ぐむことがしばしばある。眼球の粘膜が弱いのかなんなのか知らないが、非常によく涙ぐむ。だから風の強いときは勿論、壁の塗り替え直後のシンナー臭い部屋に入っても涙ぐむ。他にも訳もなく電車の中で涙ぐむこともしばしば。
まあ別に涙と云っても一滴こぼれるか否かの量だから欠伸をしたふりをして誤魔化せるのだが、人と話をしている最中にこれが来るとすこぶる困る。相手にすりゃ不気味だ。
さて、塾では夏期講習も終わり、夏期講習終了直後の定期試験の結果が気になる残暑の秋、僕は授業後先生に「職員室」に来るよう呼び出された。僕は二重の意味で「うっ」と思った。
度重なる失点に(定期試験でも偏差値60を切りかけていた)ついに降等命令が下るだろう、という予想が1つ。もう1つはあの紫煙たなびく狭い職員室に行くことだった。別に広いところなら向かいの相手がタバコを吸っても問題ない。が、密閉された狭い所で吹かされると涙が止まらなくなる。
故に僕はこのタバコ臭い職員室をなるたけ避けていたのだ。
おずおずと職員室に行く、用件はやはり降等の件だった。志望校の関係もあり、C−3に行った方が僕の為になるだろうという判断で、これには異議はなかった。数ヶ月いい体験が出来ただけで良しとしよう。
僕はずっとそう考えていた。
しかし、この煙は何だろう。僕は嫌煙論者ではないが、せめて 子供の来るところではやめてほしい。僕の目は徹夜でゲームをやった後みたいにシバシバしていきた。目が腫れるように痛い。
泣くな泣くなと念じるが、そうなるとますます涙は溢れる。
眼が乾けば涙がやってくるのは理の当然であるが、場所が場所であるだけに僕は熱い目を何度も閉じて涙が漏れるのを防いだ。
そうしてなんとか数十分の慰めとも激励ともつかぬ説教を聞いて僕は泣かずに辞去した。一刻も早く、顔を洗って煙を目から洗い流してさっぱりしたかった。
僕は急いでトイレに入って顔を洗った。と、洗面所の鏡を見て僕は驚いた。
そこにいたのは一晩中泣きはらしたような瞼をした僕だった。
「山田はC−2を落とされて泣いた」という噂は若干塾内を駆けめぐったようだが、さすが知的の府だけあって、学業の妨げになるほどではなかった。 ▲
|
| その後の塾ライフ |
|
等身大の生活
さて、C−2クラスから降等を命じられた僕は次にC−3クラスに編入することになった。なんでC−1じゃなくてC−3なのかはよくわからない。人員が空いていたと云うくらいの理由だろう。
僕がC−2にいた4ヶ月の間に、このC−3クラスのメンバーも替わっていてC−3とはいえども前のC−1クラスの時に仲良しになった人も結構いた。C−1とC−3は開講曜日が違うので、都合でチェンジすることもできたのだ。
だから、僕が落ちてきたときは知った顔が歓迎してくれた。
それも落ちたことをからかうような口調ではなく「お前、あのクラスによく4ヶ月もいられたなあ」という羨望に近い口調だった。2ヶ月程度で落とされるのが何人もいたのだ。
そのお陰で僕は難なく新しいクラスに溶け込み、それまでと同じように算数には苦戦したが、その他はおおむねマイペースで勉強を続けることが出来た。
等身大のクラス、等身大のカリキュラム、そして等身大の友達。
以後、受験が到来し塾の講座が終了するまで、僕はこのC−3で学習することになるのだが、一番切羽詰まった時期にも関わらず、僕はこの時期が一番楽しかった。
そしてこのクラスの相当数が僕と同じ中学校に進み、同じ高校に上がり、その中の何人かは今でも大事な友人である。 ▲
|
| マザコンの頃 |
|
マザー
小学校6年生といえばもうこれは立派な反抗期である。
例に漏れず僕も猛烈な反抗期を迎えていて、暇さえあれば親と怒鳴りあい殴り合い蹴飛ばしあっていた。母はともかくとして、よく武道に造詣のある父親に喧嘩を挑んで殺されなかったものだ。
喧嘩の理由なんて大したことはない。子供の論理なんて書くのも恥ずかしいものだ。
これに対して母親は暇さえあれば「即刻塾を辞めさせてやるから公立中学に通いなさい」と脅す始末、こんな脅迫が事態の解決になるわけはなく、この後は大喧嘩が始まるのだ。
僕は公立中学に通うことは僕は何が何でも避けたかった。
なんといっても塾で知的環境の快楽にはまってしまったのだ。
その頃、既に完全に見下していた公立小学校の如き理の通らない魯鈍集団とつきあう気はなかったし、生徒を丸刈りにしたり、竹刀で脅したり、物差し持って校門で待ちかまえてるような教師のいる学校なんて行きたくなかった。
はっきり言えば公立中のイメージは恐怖の巣窟だったのだ。
私立中に入ると「公立に進めば殺されていただろう」という文吏型のひ弱な知識人に随分あった。そこまで酷くはないが、僕も一時の疑似フリョー生活のせいで、不穏な噂を聞いていたのだ。公立に入った日が命日くらいには妄想を膨らませていたかもしれない。
そんな中、受験を3月後に控え、母親と殺し合い一歩手前までの大喧嘩をやらかしてしまった。母は怒り狂い、公立中学の制服申込書にサインして提出してしまったのだ。
僕は大いに怯え、かといって今更頭も下げられず、何をしたか?
笑ってはいけない、ハンストをしたのだ。
3日ばかり続いたかな? 公立に行くくらいなら死んだ方がマシ、という甚だ子供っぽい意志表示だったのだ。ついでに勉強もその間はやめてしまった。公立ではやらなくても優等生の座は保証されていたし、大体死ぬつもり(?)の人間が勉強など必要だろうか?
結局母が折れて、塾への再開と制服の取消の言質を取り、再び僕は普段の生活に戻った。
ところがここで母親である。どうもこれは僕も遺伝しているのだが、いざというとき独力では何もできないのである。よって大して意味無いことでも親類や教師や教育本に頼るのだが、この時も塾の先生に「息子が反抗して困る」と直談判しに云ったのだ。
塾の先生だって家庭の問題持ち込まれちゃ困るわな。
母は塾のC−3の先生を捕まえて職員室で長話を始めた。その為、臨時にもう一人の先生がやってきて、その日の授業をした。当然このテの変事は噂になる。何人かが職員室へ偵察に行き「変なオバサンが喚いている」と報告してきた。
そして運悪いことに、誰かが「山田のオバサンじゃない?」と云ってきたのだ。周りの好奇の視線が突き刺さる。
僕はやむなく彼らと職員室に行き、「おい、俺があんなオバサン
の顔と似ているかい?」と強引に話題を終わらせた。いくら親子でも、すぐに解るほどそっくりな顔は、普通していない。 ▲
|
| 塾の最後っ屁 |
|
最終日
僕の住んでいた県は私立中学の受験業界ではもっとも早く受験が終わってしまうことで知られている。1月末にはすべて終わってしまうのだ。隣接県では2月1日から一斉に入試が始まり、ここらは大学の入試と変わらない。
そういうわけで塾のカリキュラム的には1月の末日まであるのだが、その頃には近隣県の受験をする一部エリート以外はすっかり入試も終わってしまい、合否の発表を心配しながら塾最後の日を迎えた。
そもそも市内の学校を単願した僕は入試も余裕のうちに終わり、合格も殆ど決まってたので、塾なんて本当は行かなくてもいいのだが「学費払ってんだから」と母の弁や「最後の日に先生が記念品くれるぜ」という級友の甘言に乗って、入試終了後も勿論のこと最終日まで参加したのだ。
最後の日、誰がどこに受かったとか落ちたとかいう噂話で教室は持ちきりだった。とはいっても結果が出てるのは未だ県内の比較的レベルの低い中堅校の話であって、メインイベンターであるC−2の秀才組はこれから本番とばかりに目の色変えて廊下を歩いていた。
僕は秀才が落ち、凡才が受かる現実などに驚きながら、パーティー感覚で最後の日を過ごした。
授業は先生も将来のことについて話してくれた。こういう時の常として僕は随分しんみりとしたが、さすがにここでは泣かなかった。なんといっても殆どの同級生は中学校でも一緒なのだ。
結局、噂の記念品は出なかった。
僕は先生にお礼を言うと、仲間と一緒に帰路に就いた。
家に帰ると、母が怒り狂っていた。
「あんた、一体、今日はどこにほっつき歩いていたの?」
「え、塾の最終日さ」母の剣幕に吃驚しながら僕。
母はさらに激高し、「カレンダー見なさい」と怒鳴った。
そこには「英検3級一次試験」と書かれていた。
4月、僕は新しい制服に袖を通し新しい生活を始めた。
ここから先は中学時代の思い出話になるのだが、そんな僕の下へ一通のチラシが舞い込んできた。塾の新入生募集のチラシで合格者一覧表がついていた。僕の中学校には僕の名前と他にあの塾で切磋琢磨した仲間の名が載っていた。
一流中学にはC−2時代の仲間の名が、他にも目を落とせばあの頃の彼らの顔が浮かんでくる。
「めでたしめでたし」
僕はそう呟いて、新しい生活を始めた。 ▲
|
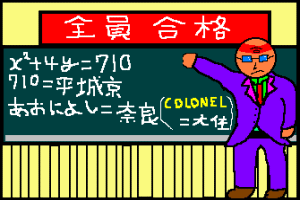
"ARE YOU OK?"
|
|