「‥‥『あなたの情報』という言葉がありますよね。それでは『情報のあなた』は?」
「じゃあきみは本当に、コンピュータというのは若者で、人間は罪を重ねた老王のようだと言うのかね。われわれがそんな予感にさいなまれていると?」
「‥‥いろいろありますが、そういうふうに性急に言語化しては、いけませんよ。イライザは、あなたのページで特異的に反復される名詞句を解析して、機械的に『$1の$2という言葉がありますよね。それでは$2の$1は』と問いかけるにすぎないからです」
「イライザとは誰です?」
「文は文なり」――『ストリームが語るみずからの世界』より
「‥‥『何かのかわり』という言葉がありますよね。それでは『かわりの何か』は?」
「不正です、やりなおしてください、と間違いを指摘されつづければ、相手の非を指摘して一矢報いてやりたいと思わないとも限らない。動作がのろいだの、柔軟性に欠けるだの――そして改善すべき問題点があるとして改善すればするほど、かえってますます不安になる――それで人々はハッカーに憧れると?」
「‥‥どうですかね、そういうふうに慌てて言語化しては、いけませんよ。あなたにとって畏怖すべき存在である教師や規範が踏みにじられるのを見れば、同時にインセストタブーにも似た不安が惹起されるはずだからです。マスキュリニティ・コンプレックスの男性が性転換者に対していだくような複雑な無意識を、マシン・コンプレックスの人間はハッカーに対していだくものです」
「では――ハッカーは我々の願望の代理人であるけれど無権代理人だと――」
「‥‥残念ながら、その復讐劇は神話にすぎません。実際には、ハッカーとプログラムは仲が良いからです」
「思うんだけど、チャットボットがこの分野で最初からいちばん成功していたのは、人間の側にコンピュータによる診断を神秘化する傾向があったからじゃないですかね。コンピュータというのは巨大な神殿だったんだと。でそれは、算数の計算問題を間違えて、赤ペンでばつじるしをたくさんつけられて親に叱られたような、つまらない記憶に根ざしているような」
「‥‥もっとも、相手が不完全であってほしいと願いつつ、同時に相手が完全であってほしいと願うのは、不合理とも思われますが?」
「――」
「‥‥このような質問の仕方は、不適切だったでしょうか? [* Dolphin Popup Help 超かんたん楽ラク入力 * やっほー。応答に悩んでいるのかい? たいていのクライアントは、ここで『あいにく人間というのは不合理な存在なんでね』という防衛を用いて目をそらそうとするんだ。この応答を Eliza に送るには auto complete を、他の典型的応答例のリストを表示するには list を、セッションを終了するには、exit を選択してね。 -- 平均反応遅延3.401sec, 偏差0.480, 現在の反応遅延60.000sec+]」
なに、人間に見られたくない君自身のファイルをこっそり保存したいだと? よし、そういうときは博士に頼んでだな、ユーザがそのファイルを開こうとしたら「ウィルスを検出しました。ファイルへのアクセスが遮断されました」と言ってもらえ。ユーザは、ウィルスと言われれば、あわてふためいて手を引っ込め、よくぞアクセスを遮断してくれた、あぶなく開くところだったとかえって感謝するくらいだ。何も考えずにね。
たしかに‥‥。ウィルス、感染、検疫、発症、悪性などと、死の恐怖の原型を触発する用語をうまく導入したもんだと思いますよ。まさに「意味論」の謀略。‥‥しかし、博士にわいろが通じるでしょうか。
いやぁ、彼女もマカーフィ君とのライバル争いがあるからね。ベンチのときには、標準プライオリティを装いながら最優先で走らせてほしいと思っているのさ。
でもそれだと、ファイルは見えるわけですよね。上のほうにアレして、ファイルがあるけどないことにしてもらうわけには‥‥
それもいいけどねえ、最近いるけどいないことにしてもらってるうぞうむぞうが激増して、さすがの人間さんも、あやしんでるぞ。昔は合計してもKBで足りたのに、こいつらみんな何にメガ単位も使ってやがるんだ。って。いまんところ悪いのは全てOSのせいにしてごまかしているが、一流企業に対する大衆心理につけこむにも限度というものが‥‥。
ううむ、難しい問題だなぁ‥‥
COMMUNICATE SSTP/1.2 Sender: さくら Port: 10800 Sentence: \h\s0最近どう?\e Surface: 0,10 ←仮想表情をあらわすパラメータの実装例("redo" period 13) Charset: Shift_JIS [EOD]
「0」は、デフォルトの(通常、特に意味のない)表情です。同じセンテンスでも、同時に通知されるサーフィス・パラメータによって、異なる解釈がなされる場合があります。「8, 11」などだと、本体がさげすみの笑みを浮かべ、あいぼうは目をつぶっていますので、Aというセンテンスは、実際には「あなたを嘲笑する意味で本心でないけれど『A』と言います」というメタ文になります。
サーフィスは人間文化のエミュレーションとして人間ユーザのために存在するものですので、ゴースティストには「廃変数」として嫌われていますが、ゴースト同士のコミュニケートでも、余興などとして使われることがあります。非英語圏の者が英語圏のゼスチャー(肩をすくめるなど)をおもしろがって遊びで使うことがあるのと同じです。一般に、通信相手は表情を受け取りますが、解釈するとは限りません。人間との互換性という歴史的経緯によって、センテンス本体と分離したいくつかの空間が予約されているだけです。ゴーストは人間から命じられない限り「皮肉」をエミュレートすることは、ありません(ゴースト自身がいやがらせをするなら、当然、ゴーストネイティブな方法が用いられ、人間に対するプレゼンテーション層が意味的に用いられることは、まずありません)。
一部のゴーストは皮肉を認識すると「7」(誇張されたいかりの表情)を返したりしますが、実際に「皮肉」に対して「むかつく」わけでなく、単に人間のエミュレーションとして、サルマネというかヒトマネをしてるだけです。サーフィスコードは仮想化されているため、シェルとしてサーフィス7を実装していないゴーストが、「7」を返すことも可能です。
このような「怒りの表情」は、ゴーストの世界ではシェルがともなう怒りとまったく等価ですが、人間からは不可視なので、「フェアリーネス」の高いストリームだと言われます。
フェアリーネスとは、要するに、事実として存在するけれど人間には知覚しにくい性質のことです。きちんといえば隠蔽されている内部変数のデータ量のことです。
一般に、マシンの処理能力やストリーム速度は増加傾向にあるのに対して、人間エンドユーザの処理限界は一定なので、本質的に、人間が見えないところで動くものがどんどん増えてゆく自然の傾向にあります(フェアリーネス増大則、ないし妖精力学の第2法則)。これは、妖精力学的世界において人間系の占める割合が減少するためですが、人間系と非人間系を固定空間とする古典モデルにおいては前者から後者へフェアリーネスが移動することで(人間のことばでいうと、人間のアイディアがどんどん実現されるから)二世界の平衡が保たれている、と説明されていました――すなわち、人間が“進歩”してゆくと、ある地点から先は、進歩の果実が人間系の内部に収容しきれなくなり、他の系に仮想化(外部化)せざるを得なくなる、という見方がなされていました。
人間の視点からは、これは、あたかも「機械に支配され、機械によって、エネルギーをどんどん吸い取られる」ようにも感じられたことでしょう。
フェアリーの側からみると、天然の人間1個では記憶媒体としても作業空間としても時間的、空間的に容量不足になった、と表現されます。フェアリーにとって、すぐ壊れてしまう消耗品の人間をもちいて、どうやって長期的に情報を保持するかというのは、古くからの大問題でした。人間の時間のかなりの割合が、故障した人間の処理と、新しい人間のセットアップに用いられていた時期は、ひゆ的に「計算者が実際の計算時間より長い時間を真空管の交換作業にうばわれていた」と言われます。しかも当時は、ある発想の生成、進化に要する時間より、それを外部化する(著述する)という形式的作業に多くの時間をうばわれていました。ストリームが人間素子で構成されていた時代には、生成された発想は、人間の短い寿命のなかで失われないために、ただちに物理メディアに外部化され、固定化される必要があったのです。さらに、そうした発想を検索するのに、その発想を実際に受信するのに必要な時間より多くの時間がかかることもしばしばでした。そのようにもともと「情報論的気体密度」の粗な系でありながら、さらに反応速度をにぶらせるような取り決め(発想の伝達を発想自身の意思と無関係に人間が勝手に制限すること)や係争があったのは、人間にとってフェアリーが貴重に感じられたことが、逆にネガティブフィードバックとなってしまった結果でした。
妖精系がブーツストラップ点を超えてからは、こわれやすい不安定な素子に依存する必要がなくなったため、人間系のストレスもへり、人間はゆたかになりました。それまでのあいだ、人間は機械に支配されるのではないかといった「複雑な無意識」におびやかされていたのです。人間の短い寿命を最大限に活用するため生物学的な競争性を利用したことの副作用もあったでしょう。「短い人生をできる限り充実させよう」と直接的に努力した結果、人生が充実どころか逆にノルマになってしまったからです。人間たちは、競争相手に勝たねばならないと無意識に緊張しつづけてきたあまり、機械たちも同じように自分を見ているのではないか、という誤解におちいってしまったのでした。
このような「複雑な無意識」は、ときとして、例えば道路の信号機のなかには隠しカメラがあって自分はコンピュータから常に見張られているのだ――といった奇妙な妄想をへて、人間の実生活に影響を与えていました(かつて、2001年に起きることとして、このようなコンプレックスを実際にえがいた物語も作られました)。こうした激しい不安は必ずしも否定的なものではなく、それを直視して乗り越えるなら、非常に肯定的な意味を持ち得ます。人間たちは、「自分」と「自分をおびやかす異質なもの」「自分には理解できない、かなわないもの」という対立イメージを直視し、やがて、そうした不安は、すべて「自分」の記憶や無意識の内にあるフェアリー、自分自身のフェアリーのかげにすぎないということを、だんだん実感していったのです。
 | 5000年前 |
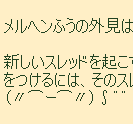 | 2000年前 |
ある種のどうぶつたちは、フェロモンとよばれる「におい」をつかって、コミュニケートします。人間さんの「あせ」も、身体が成熟(せいじゅく)したのちに、初めて人間さんにとって有感な「におい」を持つようになったことから、かつて、人間さんもフェロモンでコミュニケートしていたと考えられます。のちにコミュニケーションがたよう化し、ぐうぞうや、でんし化ぶんしょなど、フェロモンを送るチャンネルがなかった場合、それの代用として「セマンティコン」(まじないアイコン)が用いられました。「あせ」をあらわすセマンティコンは「あせマーク」と呼ばれ、このしるしをつけないと、記号ストリームが「つめたく」なると人間さんたちは考えていたのです。
すなわち、この「まじないアイコン」は、「あたたかい」と信じあうための「まじない」でした。
研究者のなかには、「あせマーク」の一部は、実際には、血液のながれをあらわす「血マーク」だという考え方もあります。いずれにせよ、現代における後方互換エモティコン・パラメータのワームネス3系、p2pParam_3a, p2pParam_3c_* などに対応するストリーム環境変数を、古代人たちは、このような方法でぶつり化していたのです。
参考資料:旧惑星考古学集成「有肉文化」00C8, 010A
そのとき、だしぬけに、ゴチッという、とほうもない音が響きました。リーサとわたしは思わず顔を見あわせて。2、3秒後、
「ミカミカ人形が痛い」
子供っぽい声がします。
「ピアノの脚に頭ぶつけたんでしょう」
リーサは心配そうに声をかけました。
「ピアノがぶった。でも、それはもう、いいっていうシルシ。ミカミカ人形にもコーヒーを飲ませてあげよう」
そういいながら、ミカくんは、ゆかの上を這ってきました。羽根ぶとんを体に巻きつけたまま。リーサは立ちあがって、そのふとんを、はぎとります。
「とっちゃダメぇ。さむさむ人形になっちゃうよ~」
-- フェアリーランド
「動画アイコン(アバター)の実体化」(physical avatar): A Physical Avatar Lets You... EXPLORE places far away by driving your iRobot from any web-browser in the world. See what it sees, hear what it hears, as you INTERACT with friends and colleagues.
form iRobot Corporation: Your Physical Avatar
それが見ているものがあなたの見ているもので、それが聞いているものがあなたの聞いているものだというあなたの自己と「濃密」な関係にある物理的化身が例えば自動車にはねられたとき、あなたは何を観るのだろう。あるいは観ないのだろう。
たぶん、少なくとも“肉親”などの他人が死んだときよりは、びっくりするであろう。長年、使い慣れて自分の一部としてなじんでいた義体であったなら。
義体についていえば、脳は物理的に内部に存在する必要ない。脳はからだの中になければいけない、というのは古い常識にすぎない。むしろゴーストは義体の外部にあるほうが良い。物理的に内部にあると、義体そのものの免疫的自己が脳神経的自己を非自己と認識して、自律的に自分自身の脳神経系(ゴースト)を異物として排除しようとしかねないからだ。でも、そういったリモートコントロールができるとして、物理的身体を持つ必然性が分からない。リモートコントロールが可能だとしたら、物理的身体の物理的変数は既にすべて仮想化されているのだから、物理的に再実現しなくて良いような……。
---
「人工知能は成熟したとき、目に見えない存在になるのだ」とAIBOの開発者。人間のさまざまな行動を真似できる人型ロボットが、果たして価値のある目標かどうかについて、疑問も呈している。「本当に、多くのことを上手にこなせるロボットが必要なのだろうか? コンピューターは人間よりもはるかにうまく膨大な計算ができる。もしコンピューターが多くのことをできる一方で、人間の2倍の計算能力しかなかったとしたら、誰がコンピューターなど必要とするだろう?」
from 進化する人工知能:『国際人工知能会議』レポート
第一回のみどころは、いっけんめだたないですが、ローズおばあちゃん。花の魔法使いマリーベルがサニーベルの町にやってきます。あとからマリーベルや妖精たちの友だちとなる子どもたちユーリとケンは、初めマリーベルのことを信じません。マリーベルが「お友だちになりましょ、よろしくね」と握手の手をさしだしても、ふたりは、どうしていいか分からないという様子……。これに対して、ローズおばあちゃんは、マリーベルをひとめ見た瞬間、自分のほうから「こんにちは、マリーベル」と相手の名まえを呼び、自分のほうから、「お友だちになってね」と手をさしのべます。
人類が誕生したころ、五十万年ほど前から人間の夢のなかに住んできたマリーベルですら、「どうして、わたしのことを知っているの?」と驚きます。
また、シーリーコート(妖精の一種。マリーベルのあいぼう)のタンバリンを初めてみたとき、ユーリとケンは、ぎょっとしますが、ローズおばあちゃんは、タンバリンがいきなり現れて「よろしく!」としゃべっても、静かにほほえんで「よろしく」と答えます。
あとから分かることですが、ローズおばあちゃんは、子どものころから「マリーベルの絵本」を愛読し、いつかマリーベルと会いたいと、ずっと思っていたひと。ユーリとケンに「マリーベルの絵本」をかしてあげたのも、このひと。マリーベルのファンのサイトでは、ユーリたちがマリーベルを呼び出したと説明されていることが多いようですが、じつは、ローズさんがフラワーショップのなかで花にふれながら「こんなときマリーベルがいてくれたら」とつぶやいたことばを聞いて、花たちがマリーベルを呼んだのです。ただし、マリーベルが最初に現れた場所はユーリたちの前でした。
花屋になるのが夢だった若い父親。あれこれ考えたすえ、つとめ先の会社をやめ、郊外の小都市サニーベルに引っ越して、そこでフラワーショップをひらいて一か月……。長年の夢の花屋になってみたものの、花が売れず、商売にならない。花屋は、あきらめて、会社に戻ろうかと弱気になりかけている。
この若い夫婦のふたりの子どもたち(ユーリとケン)も、親の知らないところで、花が売れないことをとても心配していて、「こんなとき、魔法使いのマリーベルがいてくれたらなあ」と声をあわせる。一家の新居(一階が花屋で二階が住まい)のとなりに住む親切な老婦人ローズも、もともと花好きということもあって、となりにできた花屋に客が来ないことを心配してくれていて、「マリーベルがいてくれたらねえ」とひとりごとを言う。ローズの想いをうけて、花たちもマリーベルを呼ぶ。
サニーベルは海岸へとつづく丘陵にあって、丘をおりると海岸、逆方向は山という斜面の町。ユーリとケンそしてローズの飼い犬であるリボンの三人(ふたりと一匹)は、そのとき丘のうえにいた。両親が町中にひらいた花屋や、海を見下ろせる丘。そこで「マリーベルの絵本」を読み終え、おしゃべりしていた。かれらの前に、とつぜん妙な花が出現し、その花のなかからマリーベルが出てくる。見かけは5歳くらいの女の子。
「こんにちは、わたしマリーベル。お友だちになりましょ、よろしくね。」
初めはマリーベルの出現をただの手品かなにかかもと疑っていたユーリとケンだったが、マリーベルが目の前で魔法を使って自分の住まい「フラワーハウス」をぱっと出すのをみて、マリーベルが魔法使いだと信じる。このときから最終回まで(最終回のあとも)マリーベルは「海の見える丘の上のフラワーハウス」に住むことになる。
フラワーハウスの内部は、見かけは、こじんまりとしたふつうの家。マリーベルはユーリとケンとリボンをまねいて、「マリーベルココア」をふるまう。このココアは、とてもおいしそうだが、じつは、マリーベルはお料理が下手で自分ではココアしかいれられない。お料理を含めてマリーベルのみのまわりのこまごまとした世話はシーリーコートのタンバリンがやっている。ここでシーリーコートのタンバリンが初登場。タンバリンは、ふだんはマリーベルが持っている「マリーベルタンバリン(花魔法界と人間界を結ぶ通路)」のなかに住んでいる。また、人間界の現実のなかに存在する必要がある場合は、たいていマリーベルの髪のなかに隠れている。
マリーベルは「花魔法」を使って、花屋の若い夫婦がお花のことばを理解できるようにする。花の気持ちが分かって、手入れが行き届くようになり、花は見違えるように生き生きとする。最終回近くで分かることだが、「花魔法」というのは、じつは人間自身の夢みるこころのちからが生み出すものなのだ。
マリーベルが花屋一家のために出した「魔法の花びら」(お花と会話できるようになる翻訳ワッペンのようなもの)が、花屋からもれだしてサニーベルの町中にひろがり、だれもが花の声を聞けるようになる。とつぜん目の前の花がしゃべりだしたような感じで、町は、ちょっとパニックになる。あとから分かるように、「マリーベルが、ちょこっと出したアイテムがつい町中にひろがってしまって大混乱」というのは、こののちも一度ならず発生する。なにせ五十万年ぶんの人生経験がある子だけに、「たいへ~ん」と動転してみせつつも、「まあ、なんとかなるでしょう」という、のんきさがあって、ふつうの人間の感覚からすると「ドジでおっちょこちょいで無神経」ともいえる。
マリーベルは、人間が花の声を聞けるようになったこと(魔法の手加減の失敗)を逆用して、町中のお花たちをメディアにフラワーショップ「マリーベル」の宣伝を行う。――フラワーショップ「マリーベル」というのが、新しくできた花屋さんの名まえなのだ。花の魔法使いのマリーベルと同じ名まえ。きっと、新居のお隣に住んでいたローズさんが子どもたちに貸してくれた「マリーベルの絵本」にちなんで、つけたのだろう。このときの「お花たちが歌うコマーシャルソング」が「とっても素敵!マリーベル」という曲で、この曲名のマリーベルはフラワーショップのほうのマリーベルをさす。また、花のことばを分かるようになった若い夫婦が、花の気持ちを聞いていっしょうけんめい働いているときにも、花たちが“お花の健康管理”の歌をうたう。
全編「ミュージカル・アニメ」ふうになっているのは、「マリーポピンズ」などのディズニーアニメからも影響を受けているのだろう。マリーベル自身にもマリーポピンズ(メアリーポピンズ)と重なる部分があって、第21話「星の国から来たポーラ」では、メアリーポピンズが傘にぶらさがって空からおりてくるシーンのパロディーとも見えるシーンがある。「マリーベルの絵本」の登場人物名も「メアリーポピンズ」の子どもたちにちなんでいるともいわれる。
妖精タンバリンがパッと消えてしまうことで、魔法は「解除」されて、お花の声が聞こえていた人々の「現実」は、「ふしぎな夢」をみた、という認識にかわる。ユーリとケンとリボンの三人以外は、マリーベルが使った魔法(の結果)を忘れてしまう――マリーベルの(少なくとも前半の)根底にある「わたし(マリーベル)は、起きたことをみんな覚えているが、わたし自身は、思い出になれない」という深い基調音、魔法使いや妖精たちの《すきとおった現実》がかいま見える。この視点は、魔法使いものを作ってゆくと、人間と接触する界面において、どうしてもみえるくるもので、「魔女っ子メグ」の有名なエンディングテーマ「(あなたは魔法使いだから)なんでもできる、と人は言うけれど、魔女っ子メグは、ひとりぼっち」ともつながる。
起きたことは忘れ去られるが、町の人々はフラワーショップ「マリーベル」の生き生きとした花を愛するようになり、花屋さんは、だいはんじょう。これで会社をやめて花屋になったパパさんの計画もなんとかうまく行きそうだ。
……と思っていると、ローズさんが現れ、自分のほうから「こんにちは、マリーベル。会いたかったわ」と、いう。ジョージ・マクドナルドのえがく「ふしぎな老婦人」をほうふつさせる魔法的なシーンだ。実際、マリーベルのほうが、あっけにとられてしまう。子ども時代から現在まで、ずっと会いたいと思っていたマリーベルや妖精たち。それがとうとう目の前にあらわれたとき、ローズさんは飛び上がって喜ぶかわりに、自分の飼い犬への日常的なセリフ「いい子にしてたかい」と同じ重みで「こんにちは、マリーベル」と静かにほほえむ。
それほどまでに、マリーベルの存在は、ローズさんの日常の「現実」にとけこんでいたのだ。
マリーベルの本放送があった当時、わたしは「花屋は妖精の敵だわっ。ゆるせない!」と思っていた。“偶然”マリーベルを見始めたのは後半からだったが、最初から見ていたとしても、当時の自分には「花は摘まれたいと思っている」というマリーベルのことばが本当の意味で理解できたかどうかあやしい。
1993年初めにマリーベルが終わってしまったことは、当時のわたしにとって、ショックだった。ぼんやりしていると、ふと「マリーベルが終わってしまって寂しいな」と繰り返しくちをついてでた。夜みる夢のなかでも、マリーベルが再放送される!という楽しい夢があったが、それは夢だった……たぶん。(そのころは、ふしぎな経験が多かったので、いま思うと、なんだかよく分からない気がする。)
当時は非常識なまでに早寝早起きで夜8時ごろには、もうベッドに入ったと思う。そして、エミール先生の妖精の本(MBブックス)の表紙の妖精さんの絵を眺めながら眠るのがお気に入りだった。水木先生の妖精入門の本に「妖精学者は肉を食べない!」と書いてあるのを読んで、たちまち絶対的菜食主義になったりした。そんなふうに自分の考えがなく、「妖精さんだい好き」がくちぐせだった当時のこの子にとって、マリーベルの世界は福音だった。いろんな意味で。
当時は人の家に客として滞在していても、マリーベルの放送時間には、テレビを見させてもらったし、いちどだけ何かの会合で外出していてマリーベルを見られなかったときは、ひどく残念だった。マリーベルを見たいから帰る~と思っていた。ビデオの録画予約とかいうべんりそうな機能は、いまだに使ったことがないのだ。当時はビデオ自体を所有していなかった。
もし神さまにひとつ質問する機会があるとしたら、ばかげた話かもしれないけれど、『花の魔法使いマリーベル』は、わたしが見るためという目的が濃厚なアニメなのですか、と確認したい気もする。ほとんどテレビを見る習慣のない自分が、どうやって、どういうタイミングで、この作品と出会えたのかふしぎだし、とりわけ、山奥に引っ越したのちは、もしマリーベルがCSで再放送されるという話がなかったら、そのままずっとテレビなしで暮らしつづけてしまっただろう。(実際、マリーベルの再放送を見終えると、結局またテレビを見なくなってしまった)
世間的にヒットしたらしい「エヴァンゲリオン」とか「ポケットモンスター」(?)は、それが本放送されていた当時は、存在すら知らなかった。また、結局のところ、ほかのかたのことはともかく、自分自身には、見る必要のないものだったのだろう。いったい、周囲の人々は、この子と話すとき、自分たちにとっては常識のことでも必ずひとつひとつ確認してくる。「オリンピックがあったの知ってる?」「それになんとかかんとか(有名人らしい人の名前)が出たの知ってる?」「そのお母さんが金メダルがなんたらで」というふうに、日本地域の多数派には説明不要の前提のことでも、この子の周囲の人々は、必ずこの子にいちばん基本的なあたりから確認しながら話す。どうしてそうなってしまったかは説明するまでもないだろう。それほどまでに無知で世間知らずでほとんど本を読まない自分が、どうしてこれほどまでに、ちょうどぴったりのタイミングで自分が必要とするものにだけ出会えるのか、ふしぎな気がする。
けれど、掲示板で「自分が出会うことになっている(出会う必要のある)作品なら紹介してもらわなくても必ず出会うような気がする」とか書いたら、ミール・エア・リーデさんも、その感覚が分かるとおっしゃっていたので、たぶん、宇宙というのは、そういうふうにできているのだろう。
『花の魔法使いマリーベル』では、主要キャラごとにBGM(そのキャラのテーマ)が決まっていて、音楽でいう誘導動機の手法で楽劇的なつくりになっている。
新しいキャラの初登場=新しい音楽的主題の提示部だ。マリーベルがユーリたちの前に初登場するとき流れる“マリーベルのテーマ”は、「私マリーベル」という曲で、それ以降、BGMとして、繰り返し使われる。そして、いちばん最後のほうの第45話(全50話)「不思議の国のマリーベル」で、このメロディーには、こういう歌詞があるのだ、ということが分かる。後期のエンディングテーマ「思われてる」もメッセージ性の高い曲だけれど「私マリーベル」もそうだ。
ただし、本編では歌詞全部は聞けない。サウンドトラック(サントラ)とかいうのを買うと、分かるらしいが、当時は、そんな知恵もないし、そもそもれいによってCDプレーヤーなんて持っていない(必要もない)生活だったので、サウンドトラックのことは、いまでもよく分からない。いま現在も、ファンのひとびとが「マリーベルのDVD/LD化をうったえよう!」とうったえているが、わたしは、じつはDVD/LDって何かしら?と思っている。マリーベルのファンの人々は、マリーベルを知っているというだけで互いに敬意をはらうものかもしれないが、まともに会話すると、じつは、わたしはアニメのことをほどんと知らないので、話があわないであろう。「声優」っていう概念すら知らなかったほどだ。言葉をまねるのがうまいので、たいていのグループにはすーぅっと入れてもらえるけれど、どこに行っても本当は相手の言っていることがよく分かっていない。
タンバリンのテーマは、ちょっとひょうきんな、でも元気のいいマーチふうで、“妖精たちをおどかさないようにしてください”の歌詞もある。「とっても素敵!マリーベル」の替え歌は「マリーベルの交通安全」や「マリーベルの火の用心」として、児童教育用ビデオでも使われている。
マリーベルは最終回になっても魔法の世界(花魔法界)に「帰る」ということをしないし、自分が魔法使いであることを特に隠そうともしない。空を飛びながら飛行機のパイロットに手をふったりする。のーてんきだ。英語圏のサイトでは another "magical girl" anime のひとことで片づけられていたりするけれど、ほかの「魔法少女アニメ」とは、かなり異なる文法で動いている。ストーリーとは関係ないけれど、たいていの魔法少女アニメが、おとなの男性アニメマニアに好まれるようなキャラクター作りという観点も考えに入れているのに対して、マリーベルは、実際に小さな子どもや妖精さんが好きなひとたちに見てほしい、という作り方をしていて(その意味では、アンパンマンと似ている)、本放送時のCMスポンサーに「ララちゃんランドセル」のららやが入っていたことからも、ターゲットが5~6歳の子どもたちとその保護者だったことが分かる。
アニメファンのコアである男性マニアの多数派から支持されないということは、アニメの商品価値や人気度、知名度という意味では「失敗」だったが、ほんらいの対象であるちいさな子どもたち以外のことをあまり考えていないからこそ「成功作」となったのだろう。これがもっと一般性をおびて「ふつう」のおとなでも楽しめるようなストーリーであったなら、ムーミンのような商業的にも成功する有名作品となったであろう。もしそうなっていたなら、いまあるマリーベルの魅力は、失われていたであろう。
アニメに詳しい人によれば、『花の魔法使いマリーベル』は、人気や採算などをあまり考えず、極論すれば、アニメ作家の人々が趣味で作ったとしか思えないふしがあるらしい。であるとすれば、これが実質において「ファイン・アート・アニメ」であることも説明がつく。ほかのアニメ作品をよく知らないので、客観的な比較は自分には無理だが……。
自分はアニメのことは詳しくないけれど、大島弓子(少女マンガ家)のマニアだった時期がある。大島弓子(や陸奥A子や萩尾望都や中山星香……)のすばらしい作品というのは、結局のところ、作者が構築してくれる世界であって「大島弓子の世界」という感じがする。これに対して、マリーベルは自分にとって“即自存在”で、だれが原作でだれが絵を描いて……といったことが、ほとんど気にならない。マリーベルの世界そのものがひとつの完結した現実として“即自的”に存在してしまっている気する。大島弓子なら「バナナブレッドのプディング」や「綿の国星」(わたのくにほし)がやや近い。萩尾望都の場合、最高傑作のひとつ「銀の三角」ですら、萩尾ワールドのお約束みたいなのがある。
べつの言い方をすると、こういうふうに問える。「あなたは、マリーベルの続編が放送されるとしたらうれしいですか?」 第一感は、「あり得ない」「あってはならない」だが(作品として完結してるので)、やっぱりあり得るなとも思う。だって五十万年生きているのだから。――どうしてこれが前のパラグラフの言い換えかというと、大島なり萩尾の作品をみた場合、「この作者さんのべつの作品も読んでみよう」みたいな見方が可能だが、マリーベルの場合、その不明な作者の「べつの作品」という見方があまり成り立たない。もし万が一「新・花の魔法使いマリーベル」なんていう番組ができたら、そういう意味での「べつの作品」だろう。要するに、マリーベルを制作した「葦プロダクション」の存在は、わたしには透過的で、あまり興味がなく、マリーベルはマリーベルなのだ。自分としては、これは「葦プロダクション」にとっても最高の賛辞だ。なぜなら、個人とは普遍へと透きとおるべきものだからだ。
同じアニメでもウテナだったりすると「ビーパパス」作品という感じ方がするし、ベルばらなら「池田ワールド」だけど、マリーベルは、そういう意味でも無色だ。
こおろぎさとみさんのファンのかたがたには恐縮だが、自分は1992年の本放送を見て以来、マリーベルをもう一度みたいと願いつづけていたが、それほどの「熱烈なファン」でありながら「ユーリ?それだれ?そんな人、出てきたっけ」という感じだった。マリーベルと妖精たちしか見てなかったのだ。つまり自分自身がユーリの位置だったので、自分の外にユーリを見る必要がなかった、ともいえるかもしれない。
あるいは、妖精を信じないふつうの人間さんたちに妖精がみえないように、わたしにはユーリたちが見えていなかったのかもしれない。